ハインリッヒの法則
1件の重傷事故の背景には、29件の同種の軽傷事故、300件の障害のない事故が存在するという法則で、 交通安全教育にはひんぱんに持ち出されます。(ヒヤリ・ハットの法則)
| 1件の事故に対し、事故になりかねないヒヤリが30倍存在する ↓↓↓ だから事故になる前に取締るんだ!(by 警察) |
こうして交通規制とその取締りは正当化され、厳しくなる一方です。しかしその厳しい規制/取締りの結果はどうだろう?
| 厳しいシートベルトの取締りを行うことが、 「点数を切られないためにシートベルトをつける習慣」をつけ、 厳しい速度取締りによって、 警察の前ではおとなしく、警察がいなければ我が世の春を謳歌する。 |
こんなところではないでしょうか?
ドライバーの経験則
「ハインリッヒの法則」を管理者(警察)の目ではなく、ドライバーの視点から見てみよう。
運転中は、ほんの一瞬の判断ミスで事故となる場合があります。しかし、だからといって、ハンドルを握っている間、ずっと神経を研ぎ澄ませて運転することはできません。そしてドライバーは、意識するしないに関わらず、注意力を高める場面を選択しています。「昼間より夜間」「直線よりカーブ」「晴れた日より雨の日」などなど。
このように安全運転に必要な判断力の配分を調節しながら、ドライバーはさらに学習していきます。こうした経験の積み重ねによって、事故に未然に対処するための判断力が養われていくものなのです。
つまり、1回の事故に対し、その30倍のヒヤリを経験する。そして、ひとつのヒヤリに対し、その30倍のハッとする事態を経験する。さらにひとつのハッとする状況の裏側にはその30倍の・・・。こうした経験によって、机上の論理ではなく、経験に基づいた安全運転ができるようになり、他人への配慮も可能になるのである。
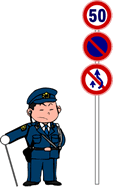
この「ドライバーの経験則」が葬られ、ただお上のルール(法令)を厳しくして「違反は違反」だとやられても警察官が嫌われるだけではないでしょうか。 また「取締り(法執行)の裏表」が、法の権威までも失わせてしまうでしょう。そうなると警察の前でだけ従順な「表裏を使い分けるドライバー」が増えるに違いありません。
警察の厳しい取締りで作られた秩序は、警察の前でしか守られない
次は、「取締り(法執行)のウラ表」について